遺言書を作成する際のリスクである遺留分の侵害の回避について解説。
今回は、遺言書を作成する際の最大の注意点である遺留分の侵害のリスクと回避について解説します。
遺言書による遺産の分配の指定
相続においては、原則として、法律で定められた法定相続人が法定相続分に従って遺産を取得することになります。(もちろん、法定相続人間の遺産分割協議により、自由に分配を決めることはできます。)
けれども、被相続人(故人)の遺志としては、特定の相続人又は第三者(知人など)に特定の遺産を譲りたいという場合もあります。
そういった場合には、遺言書を作成することにより、法定相続分と異なる遺産の分配を指定したり、法定相続人ではない第三者に遺産を贈与する(=遺贈)することができます。
つまり、遺言書を作成することによって、遺産を誰にどれくらい譲るかを自由に決めて、指定することができるのです。
また、遺言により遺産の分配を指定(=遺産分割の方法の指定)することにより、残された相続人たちが遺産の取得を巡って争うことを防止することも可能になります。
このように、遺言書の効果というのは故人の遺志を叶えるためには、大変便利なものなのですが、次に説明する遺留分に十分注意しなければ、かえって紛争を惹起する可能性があります。
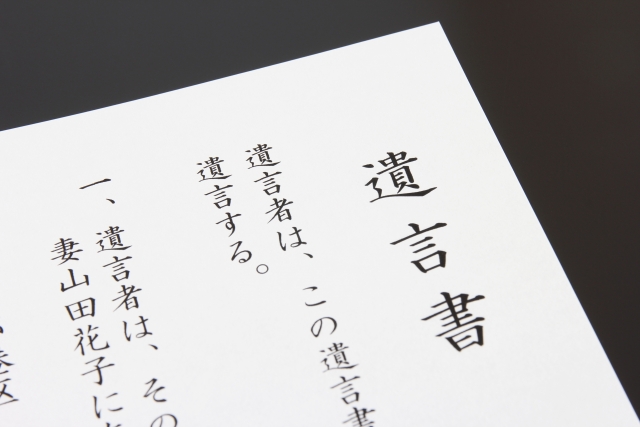
遺留分とその侵害とは
遺留分というのは、法定相続人に与えられている、相続における最低限の取り分の保障ということができます。
遺留分の額は、次の計算式によって求めることができます。
●遺留分を算定するための財産の価額(A)=(相続開始時における被相続人の積極財産の額+第三者に対する生前贈与(原則として1年以内)+相続人に対する特別受益となる生前贈与(原則として10年以内))-相続債務の全額
遺留分の額(B)=(A)×総体的遺留分割合×法定相続分
※総体的遺留分割合は、直系尊属のみが相続人の場合は1/3、子又は配偶者が相続人の場合は1/2、兄弟姉妹の場合は0
上記のように計算式は複雑ですが、誤解を恐れずに簡略化すると、子又は配偶者が相続人となる場合は、概ね、法定相続分の1/2が遺留分となるケースが多くなると思われます。
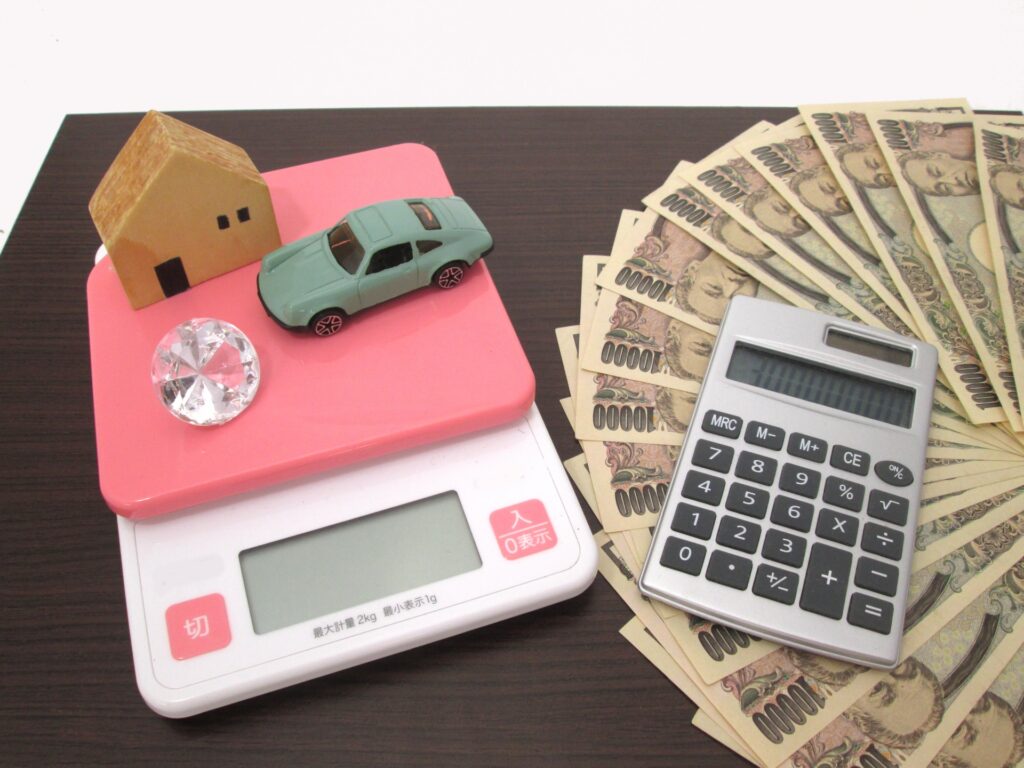
遺留分は、さらに遺留分侵害額を計算し、その侵害額について、相手方に金銭での請求ができる権利が生じます。
遺留分侵害額の計算式は、次のとおりです。
●遺留分侵害額={(B)-(遺留分権利者が受けた遺贈又は特別受益の価額+遺留分権利者が取得すべき遺産の価額)}+遺留分権利者承継債務の額
※上記の「遺贈」には、相続させる旨の遺言や相続分の指定を含みます。
上記式は複雑ですが、誤解を恐れずに簡略化して説明すると、相続での取り分が遺留分の額を下回った場合、遺留分侵害額請求が可能となるということにはなります。
簡略化した例にしてみると、子又は配偶者の相続での取り分が、1/4を下回ると、遺留分を侵害するケースが生じてくるということになります。
以上、複雑な式などを色々と書きましたが、遺言によって遺産の分配を指定した結果、法定相続人の遺留分を侵害したときは、遺留分侵害額請求を巡って紛争(訴訟)となるリスクが生じる可能性があるということになります。
以下、遺言書を作成する際の、遺留分リスクの回避方法について解説します。

遺言書を作成する際の遺留分リスクの回避方法
遺言書を作成する際は、上記の式によって計算される遺留分侵害額を請求されるリスクの回避を検討する必要が生じます。
手法としては、以下のものがあります。
① 遺留分を持つ相続人に対しては、最低限の遺産を取得させる(分配する)ことによって、遺留分侵害額を0にする。
② 遺留分を持つ相続人に対して、生前に財産を先渡しすることにより、遺留分放棄の許可を裁判所で取得しておく。
③ 遺言書の付言事項において、相続人間で遺留分を巡って争わないようにクギを刺す。
④ 生命保険を使って遺産を減らしておく。
⑤ 遺贈について遺留分侵害額請求を受ける順番を遺言で指定する。
⑥ なるべく若いうちに生前贈与しておく。(亡くなる10年前までに)
上記①と②には、できるのであれば対策としては有効ですが、③については法的な強制力はありません。情に訴えるだけなので、失敗する可能性もあります。
④については、生命保険の受取金は遺産ではなく受取人の固有の財産となることを上手く利用して、生前に保険に加入します。これは相続税対策にもなるのでお勧めです。
⑤については、民法で定められた法定の効果がある対策になります。
⑥については、コントロールは難しいですが、被相続人の死亡の10年以上前の贈与は、遺留分の対象とならない点を上手く利用する方法です。
以上、遺言書の作成と遺留分のリスクと回避について解説しました。
解説をお読み頂いてお分かりになったと思いますが、遺留分の計算や対策の構築は、専門的になりますので弊所の司法書士にご相談ください。


