特別受益の評価時点は「相続開始時」。現金と不動産の違いとは?
特別受益(民法903条)は、生前贈与や遺贈によって一部の相続人が優遇されていた場合、その分を「相続分の前渡し」とみなして相続人間の公平を図る制度です。
計算上は、贈与・遺贈された財産を相続開始時点の価額に引き直して遺産に組み込み、具体的相続分を算定します。この評価方法が、現金と不動産という財産の性質の違いを際立たせます。(最判昭51・3・18)
現金の特別受益――物価スライドという補正の必要性
現金は名目額が分かりやすい反面、インフレによる実質価値の変動を無視できません。
そこで実務上は、消費者物価指数(CPI)を用いて「物価スライド」補正を行い、相続開始時点の購買力に換算し、特別受益額を評価します。
例えば、10年前に500万円を受け取った長男がいる場合、同期間のCPIが1.12なら500万円×1.12=560万円として特別受益額に加算します。これにより、現金が時間価値を失った分を補い、他の相続人との実質的公平を図ることができます。
つまり、生前贈与を受けていた相続人は、インフレによって、特別受益額が増加しますので、死亡時点の遺産については他の相続人の取り分が増えるということです。
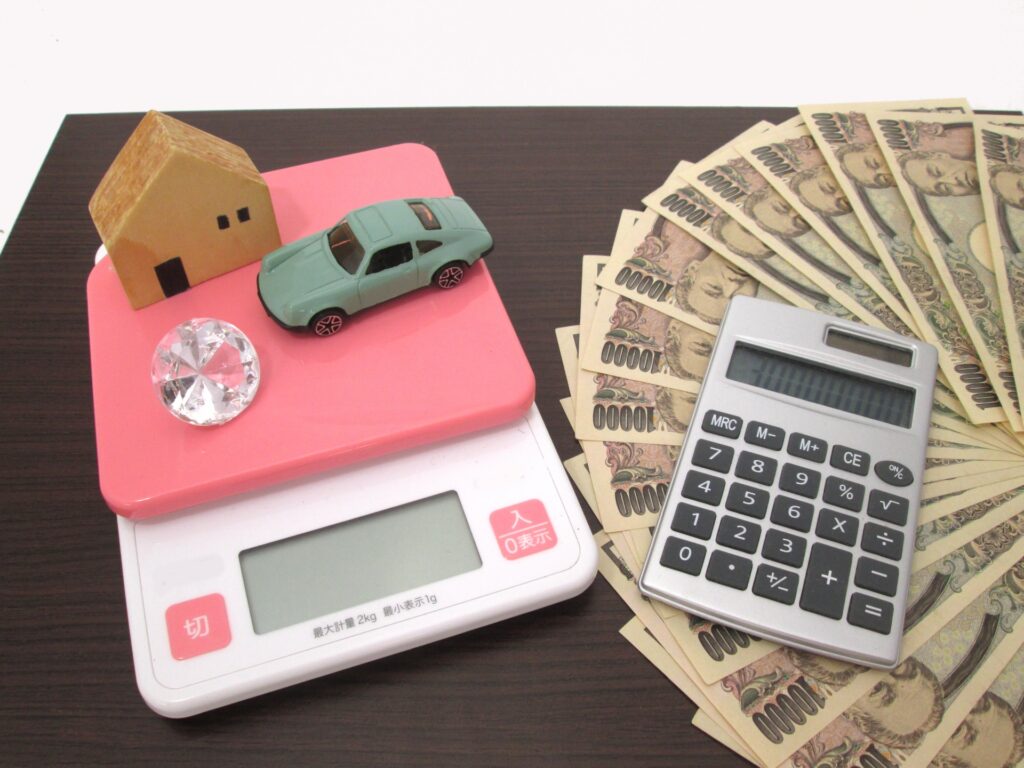
不動産の特別受益――評価時点差が招く差額
不動産は土地・建物ともに相続開始時の時価で、特別受益額を評価します。
贈与当時2,000万円だった土地が、相続時に3,500万円へ値上がりしていれば3,500万円が持ち戻し対象となり、相続による取得分から差し引かれます。反対に1,500万円へ下落していれば、その額が評価額です。
- 評価方法:路線価、固定資産税評価額、時価評価のいずれを採用するかで数百万円単位の差が生じることも。評価額に疑義がある場合は、不動産鑑定士の鑑定の利用を検討する必要があります。
つまり、不動産の生前贈与を受けていて、その不動産が値上がりした場合には、特別受益額が増加しますので、死亡時点の遺産については他の相続人の取り分が増えるということです。(逆もまた然りです。)
評価差が引き起こす不公平と対策
現金及び不動産等の物価変動や市況変動次第で、特別受益の評価額が変動することにより、他の遺産の分配が大きく変わりある種の不公平が生じます。
- 上昇局面:特別受益となる不動産・現金等を受け取った相続人が「割を食う」
- 下落局面:特別受益となる不動産・現金等を取得していない他の相続人が「損をする」
という「運要素」が生じてしまいます。
特別受益となる贈与等を遺産に含めないための「持戻し免除の意思表示」を、贈与契約書に入れておくことで、上記のリスクを回避する(そもそもの特別受益の持戻しを回避する)ことも要検討です。

まとめ
特別受益の評価は「相続開始時」が原則ですが、現金についてはCPIによる物価スライド補正を行うことで実質価値を均衡させるのが現在の実務です。
一方、不動産は市場価格の波に左右されやすく、評価手法でもめるリスクが高い財産といえます。不動産鑑定士の評価が円滑な遺産分割の鍵となるでしょう。
相続手続きや遺産分割協議書の作成については、豊中相続相談所(豊中司法書士ふじた事務所)にご相談ください。


