相続登記・遺産分割協議をする際に気を付けるべき特別受益について解説します
相続登記や遺産分割協議のご相談を受けていると、よく表に出てこないのが「生前贈与」や「学費・住宅資金の援助」といった過去のやりとりです。
これらは民法上「特別受益(とくべつじゅえき)」と呼ばれ、扱いを間違えると、相続人同士の不信感や将来の紛争の火種になりかねません。
この記事では、相続登記・遺産分割協議を進めるうえで押さえておきたい特別受益の基本と、実務上の注意点をやさしく解説します。
1 特別受益とは何か
特別受益とは、ある相続人が被相続人(亡くなった方)から、相続分の前渡しのような経済的利益を受けている場合に、その分を考慮して最終的な取り分を調整しましょう、という仕組みです。
民法では、次のようなものが典型例とされています。
- 婚姻のための贈与(結婚の際の多額の持参金・結婚資金など)
- 生計の資本としての贈与(自宅購入資金、独立開業資金など)
- 遺贈(遺言によって特定の相続人に多くの財産を与える場合)
これらは「将来の相続分を先にもらった」と評価されるため、遺産分割の際にいったん相続財産に持ち戻して(足し戻して)から全員の取り分を計算するという考え方が取られます。
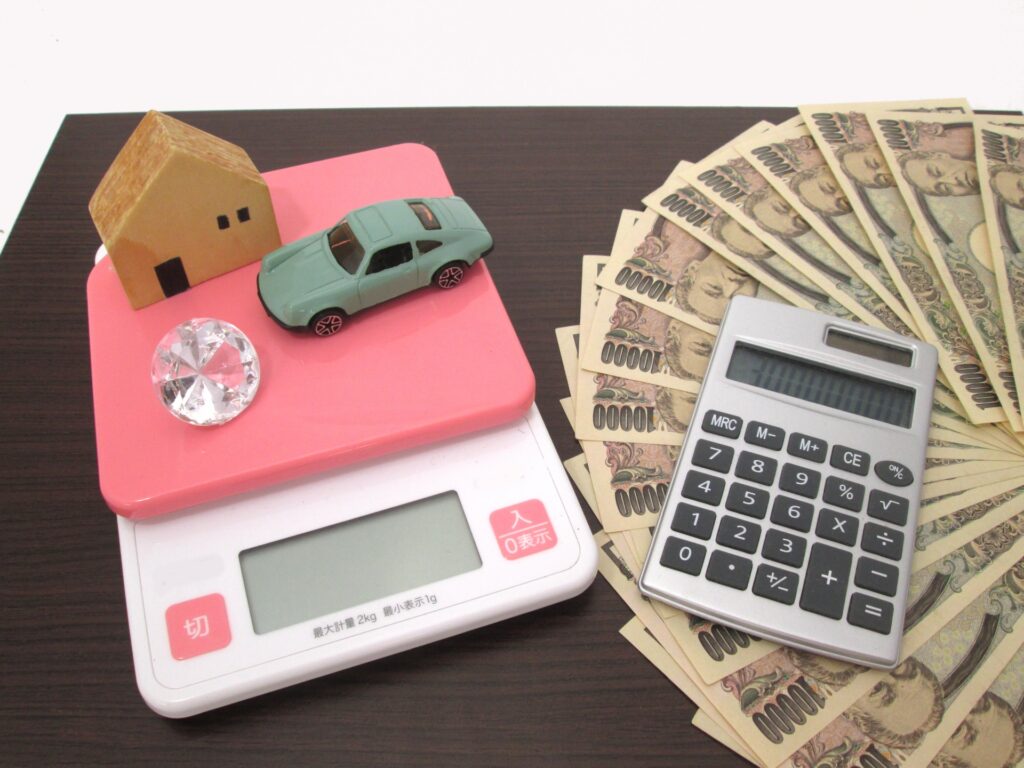
2 どこまでが特別受益になるのか
よくご質問をいただくのが、次のような費用です。
- 子どもの 学費・仕送り(通常の額の場合)
- 通常の 生活費の援助
- お祝い金(入学祝・成人祝いなど)
これらは一般的には「親として通常の扶養・教育の範囲」と考えられることが多く、特別受益とは扱わないのが原則です。
一方で、次のようなケースでは特別受益にあたりうると考えられます。
- 兄弟のうち一人だけに、住宅購入資金として1,000万円を援助した
- 一人だけに、会社設立資金・開業資金として多額の資金を出した
- 特定の子に対して、生前に不動産を無償で贈与している
ただし、「どこからが特別受益に当たるか」は金額の多寡、家族の経済状況などによっても評価が分かれます。
最終的には、相続人間での話し合いで、どう扱うか決めていくことが多いのが実務です。
3 なぜ相続登記・遺産分割で問題になるのか
相続登記のご相談では、
「とりあえず、名義だけ早く変えたいので、兄弟全員の同意はもらってきます」
というお話になることがよくあります。
もちろん、一度遺産分割協議が成立し、遺産分割協議書に署名押印をすれば、後から特別受益を主張することはできなくなるのが大原則ではあります。
しかし、遺産分割協議をする際の態様が、錯誤や詐欺、強迫に該当する場合は、当該協議の取消しの対象となる可能性があります。
- 「実は、兄だけ家を買うときに2,000万円出してもらっていたと聞いた」
- 「妹だけ大学院まで出してもらっているのに、その分を考慮していないのは不公平だ」
といった不満が噴き出し、最悪の場合は訴訟に発展することもあります。
相続登記自体は「合意内容を登記に反映する手続き」にすぎませんが、その前提となる遺産分割協議に上記のような問題があると、後からトラブルの原因になりうる点に注意が必要です。

4 特別受益を軽視しないことが、円満な相続への近道
特別受益は、相続人の感情とも深く結びつく、デリケートなテーマです。
もちろん、遺産分割協議は、相続人全員が合意すれば自由に財産の分配を決めることができますが、もし特別受益が話題に出るようであれば、特別受益を遺産に含めて(持ち戻して)協議することは必要となる場合があります。
相続登記・遺産分割協議を行う際には、
- 過去の生前贈与や大きな援助がなかったか
- それを特別受益として扱うかどうか、相続人全員が納得しているか
- 合意した内容が、協議書・登記申請にきちんと反映されているか
といった点を意識していただくことが大切です。
もちろん、特別受益を度外視して(無視)して、遺産分割協議を成立させ、自由に遺産の分配を決めることは、相続人全員が合意するのであれば可能です。
当事務所では、中立的な立場から相続人の皆さまのお話を丁寧に伺い、
特別受益の扱いも含めて、円満な遺産分割とスムーズな相続登記の実現をお手伝いしております。
「うちのケースで、どこまでが特別受益になるのか分からない」
「兄弟間で不公平感が出ないように分け方を考えたい」
といったご相談も、どうぞお気軽にお寄せください。
相続登記や遺産分割協議書の作成は、豊中相続相談所(豊中司法書士ふじた事務所)にご相談ください。


